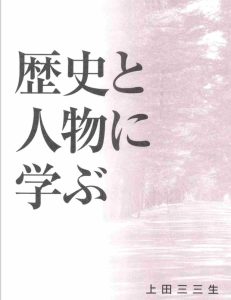原 敬
概要 ①足跡を辿ろう ②言葉にふれよう ③生き方から学ぼう さらに学ぼう

原敬(はらたかし) 1856年(安政3年)~1921年(大正10年)
盛岡藩藩士、原直治(なおはる)の次男として、盛岡城外本宮村(盛岡市本宮)に生まれる。原家は祖父の代に、藩主と血縁関係を有する家柄に準ずる「高地家格」という階級に上った名門であった。
しかし、1868年(慶応4年・明治元年)、盛岡藩は、奥羽越列藩同盟に参加し、新政府に抵抗するも敗北する。戦争に敗れた奥羽諸藩には厳しい処分が下される。原家も家禄を失い、零落していく中でも、原敬は勉学に励み成長してく。
やがて、官僚としての働きや新聞社での働きが認められ伊藤博文などからの誘いを受けて、立憲政友会に入党する。その後は、逓信大臣や内務大臣を歴任した。時には、政敵にも接近し、現実的に物事に対処する政治力を発揮し、1918年(大正7年)に、第19代総理大臣に就任する。
平民宰相と言われた原敬は、教育改善、交通整備、産業奨励、国防充実という四大政綱を打ち出し、数々の政策を実行していったが、1921年(大正10年)東京駅で刺殺され、道半ばでその生涯を閉じた。 左写真は国立国会図書館 近代 日本人の肖像より。
①原敬の足跡をたどろう →TOP
原敬の生涯、平民出身の成功、民主主義の萌芽 JV History Channel
盛岡藩家老の家に生まれ、戊辰戦争後は賊軍の汚名を着せられた原敬であったが、逆境にめげることなく精進し、自分で自分の道を切り開いていった。やがて、ジャーナリストとしてだけでなく、官僚、外交官と優秀な実務家として実績を上げ、政界に進出。政治家としての手腕を発揮し、総理大臣にまで上りつめた。近代日本に大きな足跡を残した平民宰相の人生はどのようなものであったのだろうか。
②原敬の言葉にふれよう →TOP
岩手県立図書館 子ども向け 郷土資料NO4 原敬
宝積(ほうじゃく)。聞きなれないこの言葉は、原敬の思いが込められている。どんな意味だろうか。原敬の菩提寺である大慈寺の本堂だけでなく、東京の自由民主党本部の幹事長室にも残されている。
楢山佐渡と原敬 書肆犀
戊辰戦争から数えて50年の歳月が流れた1917年(大正6年)に、盛岡で「戊辰戦争殉難者50年祭」が催され、原敬も旧藩士の一人として参加し、祭文を読み上げた。そこには、「賊軍・朝敵」の汚名を否定する考えが述べられている。
③原敬の生き方から学ぼう →TOP
平民宰相・原敬を首相に押し上げた「聞く力」 日経BizGate
戊辰戦争で敗れ賊軍となった盛岡藩の出である原敬は、決して恵まれた環境だったわけではない。内閣総理大臣になるまでには、幾度かの挫折があったが、その度に指導者としての教訓を学び取り成長していくのであった。
原敬 - NPO法人 国際留学生協会/向学新聞
本格的な政党内閣を実現した原敬であったが民衆を煽る大衆運動のリーダーではなかった。また、原敬の外交政策は、陸軍や右翼勢力から反感を持たれた。左右の両勢力から狙われ暗殺を覚悟していた原敬は、遺書まで準備していた。しかし、身辺警護を嫌い最後まで護衛は付けなかった。命の危険を感じながらも貫いた信念とは、どのようなものであったのだろうか。
さらに学ぼう →TOP
もっと知りたくなる原敬 盛岡市公式HP
岩手県盛岡市の出身の原敬。今も地元に残る原敬ゆかりの地や原敬の遺志を引き継いでいる活動について紹介している。
大慈寺
原敬の菩提寺である大慈寺。明治17年に焼失した堂宇(どうう)の山門が明治38年に原敬の支援によって再建された。盛岡市の保存建造物に指定されている。
岩手,明治,大正,政治家,TM