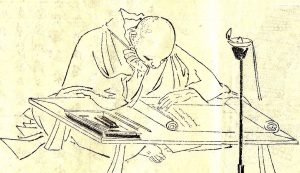阿国

阿国(おくに) 1572(元亀3)年~没年不明
出雲 阿国(いずものおくに)は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての芸能者。ややこ踊りをもとにかぶき踊りを創始した。このかぶき踊りがさまざまな変遷を経て、歌舞伎が出来上がったとされている。現在では「出雲の阿国」「出雲のお国」と表記されることが一般的だが、生存時の史料にはこのような表記は発見されていない。これらの表記は、口伝を筆記したり、彼女が伝説化してから広まったと考えられている。肖像は『阿國歌舞伎圖屏風』より。
①阿国の足跡をたどろう →TOP
『“歌舞伎”の元祖』出雲阿国の生涯 歴史の細道
出雲阿国のその生まれから、巫女としての前半生からかぶき踊りに生涯をささげた後半生、そして江戸時代の文化への影響までを解説しています。
出雲阿国について調べてみた【歌舞伎の創始者】 草の実堂
阿国はもう一人の少女とともに「ややこ踊り」という踊りを踊り、その後に「かぶき踊り」を発表しています。「かぶき踊り」は、傾奇者(かぶきもの)たちが当時流行していた茶屋遊びを楽しむ様子を演じたもので、阿国が男役を、阿国の夫・三十朗が茶屋の娘を演じたと言われています。
②阿国の生き方から学ぼう →TOP
出雲阿国 刀剣ワールド
出雲阿国は出雲大社(島根県出雲市)の巫女であったと伝えられています。京都に来るまでの人生は謎につつまれていまが、阿国の踊りが江戸時代の人々に与えたインパクトは絶大でした。すぐに全国に広まり、やがて日本が世界に誇る伝統芸能「歌舞伎」を
み出しました。
さらに学ぼう →TOP
出雲の阿国像 ニッポン旅マガジン
京都府京都市・四条大橋の東詰の園地に立っています。この近く一帯が、慶長8年(1603年)、出雲の阿国が歌舞伎踊りを初めて踊った歌舞伎のルーツと伝わっています。
出雲阿国の墓 出雲観光ガイド
出雲大社から稲佐浜へ向かう途中、山根の太鼓原の石段を登っていくと中村家の墓があり、出雲阿国の墓は石棚で囲った自然石で作られています。芸能関係者や歌舞伎ファンなど多くの参拝者がいます。
島根,安土桃山,江戸,芸術家,AH