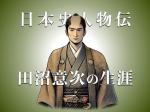田沼意次
概要 ①足跡を辿ろう ②言葉にふれよう ③生き方から学ぼう さらに学ぼう

田沼意次 たぬまおきつぐ 1719(享保4)~1788(天明8)年
父田沼意行は第8代吉宗の側近として紀州藩士から幕臣となった人物で、14歳の時に第9代将軍徳川家重の小姓となり、第10代家治の時に側用人と老中を兼任したが、失脚する。意次の執政期は「田沼時代」と呼ばれる。遠江相良藩の初代藩主(相良藩田沼家初代)
①田沼意次の足跡をたどろう →TOP
「田沼意次」はどんな人物? 賄賂政治をしたのは本当? 革新的な政策や失脚までの流れも紹介【親子で歴史を学ぶ】 | HugKum(はぐくむ)
「田沼意次の改革は、幕府と、幕府に結びつきの強い商人だけが儲もうかるしくみとなり、商人が役人にお金をわたす「わいろ」がひろまって政治が乱れました。」
悪評は、既に在職中からあり、ライバルの松平定信(寛政の改革を行った老中・白河藩主)が政権を握ると悪評一色になり、それは明治維新から戦後まで一貫して続くことになります。
しかし 一方で、時代小説家の山本周五郎が『栄花物語』で描いた田沼は、幕府の改革を行い、先進的な経済政策をはじめとした積極的な政策を推し進め、幕府を建て直した政治家として取り上げています。また、令和7年にNHKの大河ドラマで『べらぼう』が放映されていますが、田沼意次が老中として政権を担った時代は、江戸や大阪、京を中心に、町人の力が大きく伸長し、自由な気風が漲った時代でもありました。悪評と評価の混在する田沼意次とは、一体どのような人物だったのでしょうか。
田沼意次 牧之原市ホームページ
田沼意次は、御家人だった父の600石の知行を受け継ぎ、若くして将軍家重の小姓(身の回りの世話役)としてスタートしました。才能が認められ知行の加増を繰り返し、最終的には5万7千石の大名になりました。一方、幕閣においては老中首座として、今でいう総理大臣のような役職に就きます。逼迫していた幕府の財政を建て直すために、それまで幕府の収入の柱であった米による年貢に加えて、太平の世の中で台頭してきた町人らの貨幣経済や商品作物、また鉱山開発など多くの殖産興業を推奨する中で、専売制を敷き、冥加金や運上金という課税を行い、幕府の財政に貢献しました。主な事業として、印旛沼開発、蝦夷地開発、貨幣の統一など後世に大きく影響・発展する事業を展開しました。その際、「山師」と呼ばれる今で言う起業家(アントプレナー)を大いに活用して、それらの事業を着手・展開したのでした。
田沼意次が藩主となった相州相良藩(静岡県牧之原市)の地元では、名君として今でも慕われています。
②田沼意次の言葉にふれよう →TOP
田沼意次 の遺訓 『鬼平犯科帳』Who's Who
田沼意次遺訓とは田沼家の家訓として意次が作ったもので、毎年正月に家族で読んでいました。意次の堅実な性格があらわれています。
③田沼意次の生き方から学ぼう →TOP
幕府の老中・田沼意次の生涯 10代将軍・徳川家治のもとで大出世を果たし「田沼時代」を築いた敏腕政治家【日本史人物伝】 サライ
【べらぼう】「田沼意次」出世物語【大河ドラマ】戦国・小和田チャンネル
日本史上最悪とも言われる天明の大飢饉は、天明2年の天候不順から始まり、浅間山の大噴火、利根川の大洪水と重なり合い、複合災害の中で天明8年まで続きます。多くの餓死者を出したこの大飢饉は、田沼時代を終わらせるきっかけともなりましたが、一方で、田沼時代に建て直した幕府の財政の蓄えがなければこの時点で幕府は破綻していたかも知れません。しかし、未曽有の大飢饉に苦しむ人々の怨嗟の声が時の政権に向かうのは止むを得ない事でありました。
田沼意次の失脚の予兆は、天明4年(1784年)息子であり幕閣の若年寄でもあった沖知の暗殺事件からでした。そして天明6年(1786年)8月に将軍家治が死去したその翌々日、田沼意次は老中を辞職します。その後減封され、更に隠居させられ、天明8年(1788年)に不遇の内に70年の生涯を閉じました。
幕閣は、ライバルだった松平定信が老中となり、寛政の改革を始め、田沼意次の行った政治を次々と覆して行きました。しかし、その先進性は次の時代を切り拓くものであり、幕末から明治にかけて実現して行きます。「山師」が活躍し自由と独創に飛んだ時代は、次の飛躍の時を待つことになるのです。
さらに学ぼう →TOP
田沼意次|無料で読める偉人マンガ|B&G財団
わかりやすくまとめられています。
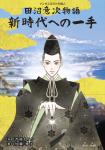
【べらぼう】田沼意次のルーツを探る 戦国・小和田チャンネル
田沼家がなぜ紀州徳川家に仕えたたのか、戦国大名の盛衰によって移動する田沼家をくわしく説明しています。
和歌山,江戸,政治家,IH