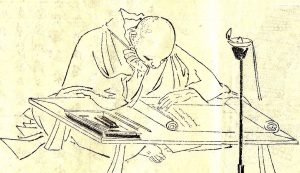上杉鷹山
概要 ①足跡を辿ろう ②言葉にふれよう ③生き方から学ぼう さらに学ぼう

上杉鷹山(うえすぎようざん) 寛延4年(1751年)~文政5年(1822年)
上杉徳治(うえすぎのりはる)は米沢藩第9代藩主です。鷹山(ようざん)は藩主隠居後の号ですが以下この呼び名で統一します。鷹山は養子として米沢藩に入り藩主となりましたが累積する借財により危機に瀕していた米沢藩を改革し立ち直らせました。江戸時代の名君と言われています。
①上杉謙信の足跡をたどろう →TOP
上杉鷹山と米沢藩
鷹山は寛延4年(1751年)に高鍋藩主秋月種美(あきづきたねみつ)の二男として江戸屋敷で生まれました。祖母が米沢藩出身という縁で10歳の時に米沢藩主上杉重定の養子となります。17歳で藩主となりましたがその時藩は20万両(約200億円)の借金に喘ぎ利息すら返せないほどでした。上杉家は豊臣秀吉から会津120万石を与えられていましたが関ヶ原の戦いで敗れた西軍についたため米沢藩30万石に削減され、さらに15万石に減封(げんぽう)されています。会津120万石時代の家臣を抱え上杉家の格式も旧のまましたので借財は膨らむばかりでした。鷹山が藩主となったのはそのような時代でした。鷹山は藩政の改革に自ら誓いを立てて臨みます。初代上杉謙信に倣って藩を挙げての大倹約に臨みます。自ら率先して実行するためにそれまで藩主の生活費の年間1500両を7分の1の209両に、奥女中も50人から9人に削減しさらに食事を一汁一菜に、衣服は木綿を着用して72歳で亡くなるまで続けました。更に倹約令と並行して藩主自らが田を耕し、範を垂れました。これを「籍田の礼(せきでんのれい)」と言います。藩主が率先して農作業を行うのですから家臣がやらないわけにはいきません。米沢藩は会津120万石時代以来の6000人の家臣団を抱えていましたのでこれらの家臣団がリーダーとなって農業改革に取り組みました。それまで稲作中心でしたが、桑、青苧(あおそ)、漆(うるし)などの栽培を奨励しました。桑の葉は絹糸を作り出す蚕の食べ物です。青苧は繊維を取り出して麻織物の原料となる植物です。漆はその樹液が接着剤や塗料となり工芸品に広く用いられます。このような作物は加工することにより藩外へ高額で販売できるのです。このようなものを換金作物と言います。安永5年(1776年)には藩校興譲館(こうじょうかん)を創設し子弟の教育の場を提供します。興譲館の教育は古い文献を考究するというより現実の政治や経済に役立つ「実学」中心の学問でした。こうして改革がスタートしたのですが順調に進んだのでありませんでした。天明2~8年(1782~1788年)の天明の大飢饉では改革が頓挫させられ。しかし、この時も飢饉に備えた備蓄米や他藩から急遽米を買い入れるなどした対策の結果他藩では多くの餓死者が出ましたが米沢藩では一人の餓死者も出なかったという事です。こうして改革の基盤を作った鷹山は天明5年(1785年)家督を治広に譲り隠居します。鷹山35歳の時でした。治広は前藩主重定の実子ですが当時鷹山の養子になっていました。隠居の身となりましたが治広の後見として引き続き藩政改革を見届けます。いわば相談役となって藩政に関与しました。鷹山の改革により藩財政は徐々に好転しましたがまだ多くの借金が残ったままでした。借財が完済されるのは鷹山の死去した文政4年(1823年)のことでした。この時、藩主は次の斉定(なりさだ)に代わっていました。
②上杉鷹山の言葉にふれよう →TOP
【上杉鷹山 歌】上杉鷹山の名歌に隠された上杉家の受け継がれた想い
鷹山が17歳で家督を継ぎ藩主となった時の和歌を紹介します。
受次ぎて国の司の身となれば忘るるまじきは民の父母
訳:米沢藩と受け継いで長となったからには人々の父母であることを決して忘れてはならない
藩主となる心構えを詠ったものですが父母の役割とはどのようなものでしょうか。
子供が小さいときにはひたすらに育み、大きくなるに従い愛情をもって成長を見守り、教育を授け間違った人間にならないように親としての姿勢を示すことでしょう。鷹山はそのように考えたのでした。民の父母として三助の考えを示します。
自助:それまで与えられる側であった藩士たちに自ら作物栽培の農作業などを行うことを奨励しました。こうして藩士たちの自立を促したのです。
互助:村単位で五人組、十人組などの組合を作り相互に協力して農作業行い今でいう落ちこぼれくを食い止めようとしました。
扶助:農作業に耐えられない高齢者には鯉の養殖を勧め、貴重なタンパク源としました。また、備蓄米制度の活用により天明の大飢饉では領内で餓死者が出なかったともいわれています。
伝国の辞/なせば成る~ 米沢城下町上杉観光
鷹山が子孫に残した言葉にに「伝国の辞」があります。伝国とは国(藩)を子孫へ伝える・継承するという意味です。
1、 国家は先祖より子孫へ伝え候国家にして我私すべき物にはこれ無く候
訳:国は先祖より子孫へ伝えられるもので自分(藩主)の私物ではない。
2、 人民は国家に属したる人民にして我私すべき物にはこれ無く候
訳:領民は国にぞくしているもので自分(藩主)の私物ではない
3、 国家人民の為に立たる君にて君の為に立たる国家人民にはこれ無く候
訳:藩主は国、国民のために存在するのであり、藩主のために国、国民が存在
するのではない。
世襲の藩主ですが自分は一時的に領国と領民を預かっている存在であり、それゆえに領国と領民に対して責任を有しているという確固とした信念があり、それを家訓のようにして子孫に残しました。霊山の考え方は現代にも通じる近代的なものでした。
次に多くの多くの日本人が知っている鷹山の言葉(和歌)を紹介します。
「なせば成る なさねば成らぬ 何事も 成らぬは人のなさぬなりけり」
訳:やろうとする意志があればできるものだ、できないのはやろうとする意志がないからだ。
鷹山の改革に対する強い意志が感じられます。改革に際しては藩内に様々な反対者が出てきますが鷹山は断固とした意思で邁進しました。強い意志を示し続けることで藩士の意識を変え領民の心構えを変え、そして米沢藩を大きく変えていったのです。
③上杉鷹山の生き方から学ぼう →TOP
【奇跡の藩改革】上杉鷹山の改革:歴史から学ぶ未来の指針【人物解説】 社会チャンネル【人物の巻】
鷹山は瀕死の状態にあった米沢藩の藩主に就任し藩政の再建に取り組みます。借金にあえいでいた財政の再建にあたって、誰もが嫌がる質素倹約をまず自分自身に課しました。自身が率先することでリーダーシップを発揮していきます。そし米沢藩の復活は財政再建で終わるのではなく藩全体の社会改革ともいえる社会全体の生活水準の向上を目指すものでした。そのために藩校を創設して教育を広め、西洋医学を学ばせ、薬草園を作って薬草の自給体制を確立させて医療を充実させ、藩全体の健康水準を高める政策を実施しました。当時の社会における基本である農業においても既存の改革以外に新田の開発を積極的に行い、更に「備籾蔵(そなえもみぐら)」と呼ばれる備蓄米制度を作って食料不足に対する危機管理制度も創設しています。鷹山の政策は短期的な利益よりも長期的な安定に主眼を置き、鷹山一代で終わるものではありませんでした。米沢藩は安定のうちに幕末期を迎えますが戊辰戦争では奥羽越列藩同盟に加わり新政府軍と対峙します。しかしその後恭順の意を示して新政府軍に加わりました。廃藩置県では一時米沢県となりますが山形県に編入され現代に至っています。
上杉鷹山 歴史と人物に学ぶ
さらに学ぼう →TOP
No.130 上杉鷹山 ~ ケネディ大統領が尊敬した政治家 (動画+読み物)国際派日本人養成講座
かつて第35代米国大統領のジョン・F・ケネディは就任の時に日本の新聞記者に「日本で最も尊敬する政治家は誰ですか」と尋ねられ「上杉鷹山」と答えました。鷹山の改革の意思、政策実行の方法等をよく知ったうえで政治家の模範と考えていたようです。
関連図書
小説 上杉鷹山 童門冬二 集英社文庫
上杉鷹山の経営学 童門冬二 PHP文庫
伝国の杜 米沢市上杉博物館
米沢市にある上杉鷹山の博物館です。
宮崎,山形,江戸,武将,AK