北条泰時
概要 ①足跡を辿ろう ②言葉にふれよう ③生き方から学ぼう さらに学ぼう
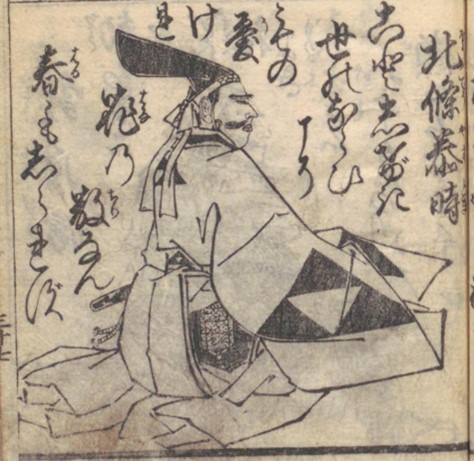
北条泰時(ほうじょうやすとき) 寿永2年(1183年)~仁治3年(1242年)
鎌倉幕府第三代執権を貞応3年(1224年)より18年間務め日本初の武家法である御成敗式目(貞永式目とも言います)を制定するなどして鎌倉幕府による武家政権を確立しました。左肖像は国書データベース 『英雄百人一首』より。
①北条泰時の足跡をたどろう →TOP
北条泰時
北条泰時は寿永2年(1183年)に第二代執権北条義時の子として生まれました。源(木曾)義仲が入京し、平家が都落ちする治承・寿永の内乱(源平合戦)の激動の時代でした。泰時の父、北条義時は源頼朝を警護するメンバーの一人に選ばれています。頼朝から信頼を得ていた父義時でしたが、少年泰時(幼名は金剛)も父同様に信頼されていました。鎌倉幕府の将軍記を記載した吾妻鑑(あずまかがみ)には泰時10歳の時の逸話が残されています。多賀寺重行という馬に乗った御家人が泰時とすれ違う時に「下馬の礼」をしなかったことに頼朝が怒りました。重行は「そのようなことはありません」と言い訳をしました。泰時に確かめたところ泰時も重行の言う通りであると答えました。しかし頼朝は重行の言葉を信用せず、逆に重行をかばう泰時の懐の深さに感嘆して愛用の日本刀を授けたといわれています。このように泰時は幼少のころから頼朝にリーダーとしての資質を認められ寵愛されるとともに期待されていました。さらに16歳の時には鶴岡八幡宮での神事流鏑馬(やぶさめ)を披露する一人に選ばれるなど源頼朝から期待されていました。
1199年に頼朝が没し鎌倉幕府二代将軍・源頼家(みなもとよりいえ)に仕えることになりますが将軍頼家や父北条泰時に意見をすることも多くなり人間的に成長していきます。その後、1202年20歳で有力御家人・三浦吉村(みうらよしむら)の娘と結婚しています。幕府内では祖父で初代執権の北条時政(ほうじょうときまさ)による二代将軍・源頼家の殺害と北条時政の失脚、そして父・北条泰時の第二代執権就任など否応なく政治の風が身辺に迫ってきます。父・北条泰時は自身の権力基盤を確立するために侍所別当(さむらいどころべっとう:軍事・警察を統括する長官)の和田義盛を討ちます。この時泰時は幕府三代将軍・源実朝(みなもとさねとも)を保護するとともに合戦の勝利に貢献しました。戦後の論功行賞でいくつかの所領を与えられますが泰時は「他の者へ与えてください」としてこれを辞退しました。この謙虚な姿勢は御家人の人望を得て侍所別当に就任し、幕府の軍事面の最高責任者の地位に着きました。
1219年三代将軍・源実朝が鶴岡八幡宮で甥の公暁(くぎょう)に暗殺される事件が起きました。これを機に後鳥羽上皇が朝廷の権威回復を図られ1221年に承久の乱(じょうきゅうのらん)といわれる反幕府反乱が発生します。33歳であった泰時は幕府軍の総大将として京都を目指して進軍します。泰時の指揮する幕府軍と朝廷軍は宇治で激突します。幕府軍は苦戦の末に京都へ入り、後鳥羽上皇は抵抗を断念して泰時追討の院宣を撤回することで戦いは終わりました。後鳥羽上皇はじめ幕府に抵抗した関係者は各地へ配流され領地も没収されました。
1224年に泰時は第三代執権に就任し幕府主導の体制を確立しました。しかしながら政治の枠組みは従来のままとしました。乱後には後鳥羽上皇の兄・守貞親王の皇子が後堀河天皇として即位し、朝廷より任命された守護が各地を統治する体制も従来のままでした。しかし内実は幕府が主導します。ここに江戸時代まで続く朝廷の権威と幕府の政治権力が並立する政治の枠組みが長く続くことになりました。泰時は1232年御成敗式目(ごせいばいしきもく貞永式目ともいう)という新たな法律を制定しました。それは土地・財産および守護・地頭の職務権限あるいはそれにかかわる訴訟などを網羅するものでした。現代でいえば民法や刑事訴訟法・刑法に相当します。御成敗式目はその写しが全国の守護・地頭に配布され武士が守るべきものとされました。泰時は法治による体制を目指したと言えるでしょう。
②北条泰時の言葉にふれよう →TOP
「巻二 新島守」(その6)─北条泰時 学問空間
後の南北朝時代に書かれた史書「増鏡(ますかがみ)」に承久の乱に泰時が父義時と別れて京都へ出陣する場面があります。別れをした翌日泰時が一人で馳せ帰ってきて尋ねます。「仮に後鳥羽院御自身が畏れ多くも鳳輦(ほうれん)を先立てて錦の御旗を上げられ、戦さの最前線に親しく臨まれた場合、どのように対処したらよろしいでしょうか。」義時は「賢くも尋ねたものだ、わが子よ。そのことだ。後鳥羽院の御輿に向かって弓を引くことは絶対に許されない。そのような時は兜を脱ぎ、弓の弦を切ってひたすら恐懼の旨を言上し、後は後鳥羽院の御判断にお任せするのみだ。そうではなくて、後鳥羽院が都に御滞在のまま、軍兵だけをお遣わしになったのなら、命を捨てて千人が一人になるまで戦え」
と答えると泰時はその最後の言葉を聞くか聞かない間に「いひも果てぬに急ぎ立ちにけり」とその一言がお聞きたかったとでもいうように再び戦場の京都へ向かったのでした。
このように清和天皇の流れをくむ源氏の鎌倉幕府の軍の棟梁である泰時は朝敵として朝廷に弓を引くことに思い悩んでいることが見て取れます。泰時の苦しい判断は幕府打倒を企てる上皇方の排除ということで自らを納得させたのでしょう。
③北条泰時の生き方から学ぼう →TOP
国際派日本人養成講座 No.1331 北条泰時 ~ 泰平の世を目指して
泰時は戦勝の論功行賞を辞退するなど諦観の心であったようです。1230年に数年来の異常気象に起因する「寛喜の飢饉(かんきのききん)」が発生し多くの餓死者が出るほどになります。泰時は富裕層に米の供出を命じその米を「出挙米」(すいこまい)とという種もみとして農民に貸し付け、利子を付けて富裕層へ返させました。ただし、非常事態であるため農民からの返済時期の延長に加え、万が一返済不能となった際には、北条泰時自身が返済する方法を採りました。年貢の免除により庶民の負担軽減を行うととともに自らも質素倹約を徹底するなど率先しました。政権を担当し、御成敗式目の制定を主導するなどした泰時は政権を担い国家国民を導くとはどのようなものかを自ら示したのでした。
さらに学ぼう →TOP
【刀剣ワールド】承久の乱|合戦・古戦場YouTube動画
承久の乱の舞台を訪ねてみましょう。
参考書籍
手に入りやすい本としては『北条泰時 頼朝に理想を実現した男』 大湊文夫 郁朋社、『北条泰時』 上横手雅敬 吉川弘文館人物叢書があります。
神奈川,鎌倉,武将,AK




